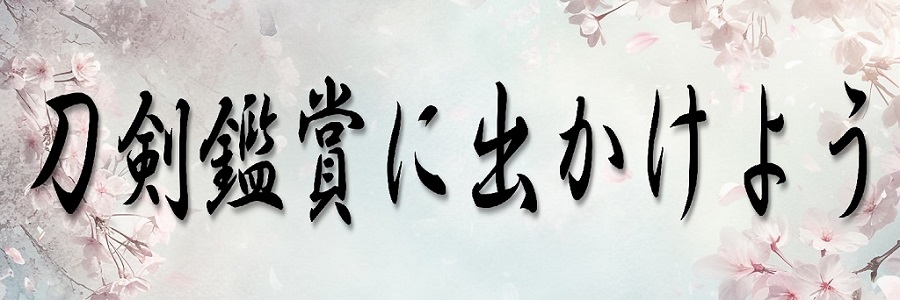日本刀の魅力Charm
刃文
焼刃の形状のことです。
大きく分けて直刃と乱刃に分かれます。
時代や流派、刀工の特徴を大きく反映しています。
具体的には鍛造後成形した刀身全体に薄く焼刃土(砥石の粉と木炭の粉などを混ぜたもの)を塗ったのち、 焼きを甘く、硬度より強度が求められる部分にさらに塗り重ね、乾燥させたうえで焼き入れを行います。
これにより鋭さと強度という相反した性質を同居させることができ、その組成の違いは肉眼によっても認められ「沸(にえ)」や「匂(におい)」と呼ばれる細かな粒子で構成されたそれを刃文と呼びます。
沸は、文様を構成する白い粒子が粗めで、肉眼で視認できる程度の大きさのものをいい、匂とは肉眼での視認が難しい程度の微粒子で、見た目は白い霞のようにみえるものをいいます。
刃文が沸主体でできていれば「沸出来」、匂い主体であれば「匂出来」と呼んでいます。

刀派の特徴が出る
よく言われているのが重花丁子は備前の一文字派に特徴的です。
また三本杉は美濃伝の孫六兼元の作品が有名。
景光は片落ち互の目が特徴と聞きます。
様々な刃文があり自分の好みの刃文を探してみてはいかがでしょうか?現在では猫や桜などを刃文に描いている刀工さんもいらっしゃいますよ。
地鉄
地鉄もしっかりとみると美しい模様があるのをご存じですか?
刀身本体を構成している地鉄の部分をじっくり観察すると、細かな文様がみえてきます。
その模様は刀剣制作の工程の折り返し鍛錬により現れます。
刃文同様に数多くの種類が存在します。
こうした地鉄の中の文様のことを、鍛え肌と呼びますが、これは刀工が作刀の際に鋼を折り返し鍛錬する方法で変わってくきます。
大和伝には柾目肌が交じる作例が多い、備前伝には板目肌に杢目が交じるものが多い、綾杉肌は出羽国月山(山形県)の刀工が得意とした・・・など、刀工の流派の特徴を示すポイントになっています。

柾目肌は木材の柾目のように平行方向に重なった模様です。 注写真は木です

杢目肌は木材の板目のようになっています。 注写真は木です
見どころ沢山
語りつくせない見どころ
刀剣の鑑賞ポイントは沢山あり語りつくせません。
全体の姿、反り、造込み、茎・切先・棟の形。やすり目や樋。パッとみただけでもそれぞれに特徴があり面白いです。
この刃文が好き、反りが・・・、切先だけ諸刃になっている・・・など、見てみると詳しい知識が無くても思いのほかその美しさに心がひかれ楽しめます。
ぜひこの機会に刀剣を見に行ってみてはいかがでしょうか。



日本刀について詳しく知りたい方は
刀剣ワールド®様のホームページがわかりやすく個人的におすすめです