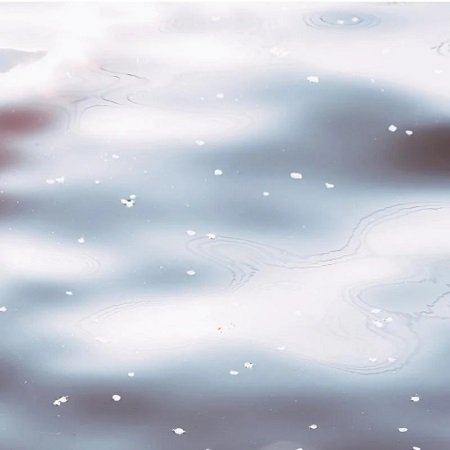童子切安綱
銘:安綱 収蔵:東京国立博物館
平安時代の伯耆国の大原の刀工・安綱作の日本刀(太刀)
大包平と共に「日本刀の東西の両横綱」と称される最も優れた名刀とされています。
源頼光が丹波国大江山に住み着いた鬼・酒呑童子の首をこの太刀で斬り落としたという伝承から「童子切」の名がつきました。
刃長2尺6寸5分(約80.3 cm)、反りハバキ元にて約1寸(3.03 cm)、横手にて約6分半(1.97 cm)、重ね(刀身の厚さ)2分(約0.6 cm)。
造り込みは鎬造、庵棟。腰反り高く小切先。地鉄は小板目が肌立ちごころとなり、地沸が厚くつき、地斑まじり、地景しきりに入ります。
刃文は小乱れで、足よく入り、砂流し、金筋入り、匂口深く小沸ついています。
帽子は小丸ごころに返り、掃き掛ける。茎は生ぶで先は栗尻。鑢目は切。目釘孔1つ。